カンとは
カンとは鳴きの一種で、同一牌を4枚そろえて槓子(カンツ)を作るための行為を槓(カン)と呼び、さらに【暗槓(アンカン)】、【明槓(ミンカン)「大明槓(ダイミンカン)と加槓(カカン)】に分けられます。
槓子(カンツ)とする4枚の牌をそれぞれの所定の形式で、自分からみて卓の右側に明かしておいた後は、嶺上牌(リンシャンパイ)を引く事ができます。嶺上牌を引いて、その時点でアガリの条件を満たしていればツモアガリすることができます。
この場合、嶺上開花という役がつきます。また、カンを行うことでドラが増えることも覚えておきましょう。2人以上でカンを4回すると流局(リュウキョク)となります。
暗槓(アンカン)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
暗槓(アンカン)はポンをしないでつくった同じ牌の4枚の組み合わせです。鳴き扱いとはなりません。暗槓(アンカン)をする場合は上のように両端の牌を裏にして、自分から見て卓の右側に置きます。
明槓(ミンカン)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
明槓(ミンカン)は暗刻(アンコー)のとき、他の人からカンしてつくった同じ牌の4枚の組み合わせです。明刻(ミンコー)からも他の人から冠すれば、明槓(ミンカン)となります。誰からカンしたか分かるように、牌をカンして、もらった人の席の位置にあたるパイを横にして、自分から見て卓の右側に明かして置きます。
明槓(ミンカン)には、大明槓(ダイミンカン)と加槓(カカン)があります。
大明槓(ダイミンカン)
手牌の中に暗子(アンコー)があり、そのまったく同種の牌(パイ)牌を他の人が捨てたときに、その牌(パイ)を使って槓子をつくることをいいます。他の人があなたの欲しい牌(パイ)を捨てた直後に、「カン」と発声してから、下の通りに手牌の中にあった3枚と捨て牌をまとめて、自分から見て卓の右側に明かして置きます。大明槓は鳴きの一種であり、一度でも行うと門前(メンゼン)ではなくなります。
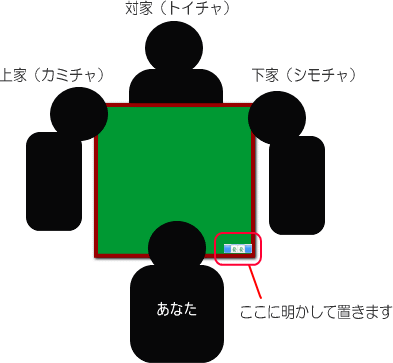
加槓(カカン)
加槓(カカン)は、すでにポンして作った明子(ミンコー)が出来ていて、それと同種の牌を持っているか、ツモした場合に、その牌を明子(ミンコー)に付け加えて槓子とすることをいいます。自摸した直後に「カン」と発声してから、手牌の中にあった1枚、またはツモして引いてきた1枚を、もともと自分から見て卓の右側に明かして置いてある明子(ミンコー)のうち横向きにしてある牌の上に重ねます。
上家(カミチャ)からカンした場合の牌の置き方
![]()
![]()
![]()
![]()
対家(トイチャ)からカンした場合の牌の置き方
下家(シモチャ)からカンした場合の牌の置き方
![]()
![]()
![]()
![]()
これで誰からカンをしたかすぐに判断する事ができます。
カンしたら忘れずに!!!
麻雀において槓(カン)を行った場合、手牌が1枚不足することになります。それを補うため、王牌(ワンパイ)の最後のところから1枚拾って補充するのですが、この王牌(ワンパイ)の最後のところから1枚の牌をリンシャン牌と呼びます。
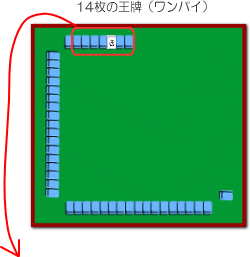
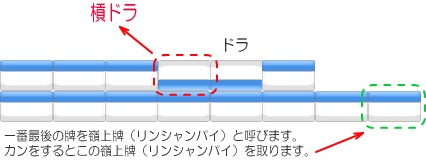
槓(カン)をしたらドラが増えます。槓(カン)をした人はドラ表示牌の隣の牌を上の図のように裏返します。
槓ドラとは
槓(カン)を行った際に、ドラ表示牌の隣の牌を裏返し、追加でドラが増えることを槓ドラと言います。槓ドラは槓を行ったプレイヤーにのみ適用されるため、槓を多く行うことで得点が大きく伸びる可能性があります。
カンの注意点
カンは特定の役を狙ったり、ドラを増やすことで得点を伸ばす効果がありますが、注意すべき点もいくつかあります。
カンは他のプレイヤーに手牌の情報を漏らすことになります。特に明槓は他のプレイヤーに自分の手牌がどのような状況であるか伝えてしまうため、慎重に判断する必要があります。
暗槓は他のプレイヤーに情報を与えないため有利ですが、鳴かずに暗刻のまま狙った役を作る方が得点が高くなることもあります。カンを行うタイミングを見極めることが重要です。
カンを行うと嶺上牌を引くことになりますが、これによって他のプレイヤーがアガリを決めることもあります。カンを行う際には、他のプレイヤーがアガリを待っている可能性を常に考慮する必要があります。
まとめ
カンは麻雀の戦術の一つであり、得点を伸ばす効果がありますが、同時にリスクも伴います。カンを行うタイミングや種類を理解し、適切な判断でカンを活用してゲームを有利に進めましょう。
